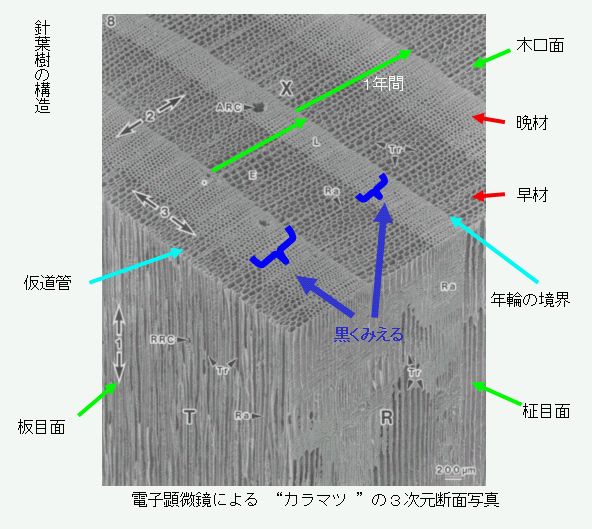
身近な年輪
森に行かなくても、年輪は皆さんの身近なところにみられます。例えば、家の柱、木の机や本棚、またコースターなど、ちょっと見渡しただけでもいくつも思い浮かんできます。凝った人になると年輪が良く見える木の薄い板で名刺を作っている人もいます。このように年輪は私たちにとって身近な存在です。ではいったいどうして年輪ができるのでしょうか。樹木などのように永い年月成長する生物では、成長が旺盛な時期とそうでない時期が周期的に繰り返すことがあります。地球の中緯度の地域に成育する樹木の場合、春には成長が旺盛で大きな細胞を作りますが、成長が衰える夏から秋にかけては小さな細胞を作ります。また、冬にはほとんど細胞を作らず休眠状態で過ごします。春にできた細胞(早材)は白っぽく、夏から秋にかけてできた細胞(晩材)は黒っぽく見えるのです。季節の変化がはっきりしている場合には年輪が顕著に現れますが、常夏の熱帯の樹木でも雨季と乾季で成長状態に差が現れるので、年輪と同じような一年周期の縞模様が現れます。
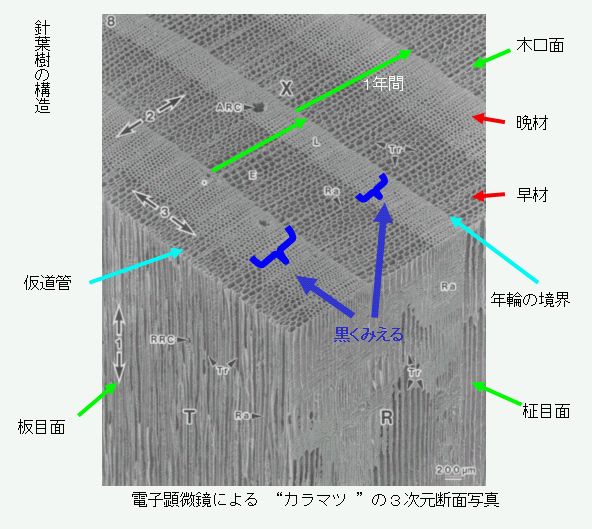
電子顕微鏡写真は「深沢和三編著(1990)樹木の年輪が持つ情報−解析技術と林業への応用−.北海道大学農学部、札幌」より引用。
年輪幅に含まれる情報
年輪ができる理由がわかったところで、年輪に含まれる情報について考えてみましょう。普通、樹木は一年毎に年輪ができますから、木の根元の年輪数を数えればその年齢がわかります。木の根元から円板を採取し、中心部分から外側に向って毎年の年輪幅を計っていきます。そうすると、初めのうちは年輪幅が広いのですが、次第に年輪幅が狭くなってくることがわかります。この現象は成長特性といって、ほとんどの生物に現れる現象です。人間でも子供のころはどんどん大きくなるのに、二十歳を過ぎるとあまり大きくならないのと同じことです。年輪をもう少し詳しく見ると、毎年の年輪幅は微妙に異なっていることがわかります。例えば、ある年の年輪幅は広いのに次の年は年輪幅が狭く、年輪幅の狭い年が何年か続いた後、また年輪幅が広くなる、というように、年輪幅は広狭を繰り返していることがわかります。
この現象は、その年の気候が温暖であったり冷涼であったりすることと密接に関連しているといわれています。つまり、年輪幅の広狭は環境の影響を受けているということです。さらに、隣合った木の片方を伐採したとき、残った木は次の年から良く成長するようになります。この場合も年輪幅が一時的に広くなります。つまり、周囲の木との競走の経過が年輪幅に現れることも知られています。このほか、木が元々持っている遺伝的特徴が年輪情報に含まれていることが知られるようになってきました。以上のように木の年輪にはたくさんの情報が含まれているのです。
なぜ年輪幅を測定するのか
林業経営者にとって所有する森林の蓄積、特に幹材積の合計を把握しておくことは資源管理の上で重要な課題であるが、毎年の収穫を量を決定するためには森林の成長量の把握が必要となる。この場合、何等かの方法で個々の林木の成長量を把握しなければならない。林木の成長量は胸高(1.2m)直径と樹高の関係から算出されるものであり、精密に調べようとする場合は樹幹解析が用いられるが、一般的には胸高直径の成長(肥大成長)だけで計算される場合が多い。肥大成長を把握する方法としては、毎年胸高直径を測定しその増加量を調べる方法などいくつかの方法があるが、成長錐(increment borer)により胸高部位から成長錐片(increment core)を採取し、この成長錐片の年輪幅の増加量を調べる方法が簡易であり一般的である。
年輪幅の連続データと肥大成長
図は高舘山のブナの胸高部の年輪幅時系列データである。連続した年輪幅データははじめの10年程ごろにピークのある変動を示し、20年以後は1〜3mm程度の変動を繰り返している。胸高直径の成長経過は図にみられるように20年生以後ほぼ直線的な傾向を示している。110年ほど経過した現在でも成長傾向に陰りがみられないことを示している。
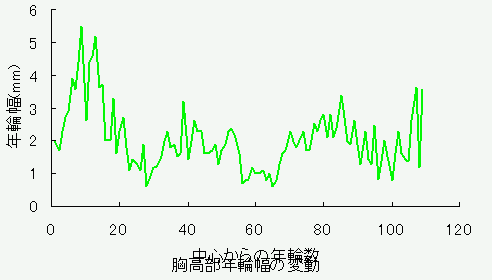
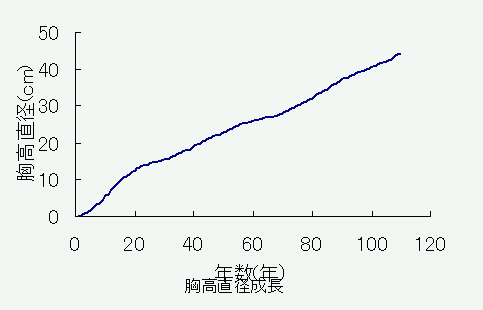
理論成長曲線に類似してはいるが、大分異なった成長傾向がみてとれる。
アテ材
年輪を良く調べると、しばしば秋にできた材ではないのに黒っぽい部分がみられることがあります。このような異常材を普通「アテ」と呼んでいます。このアテは木に異常な力が加わった場合に形成されるので、「事件を語る証拠」としてよく使われます。例えば、土砂崩れが起きて木に大きな力が加わると、その年の年輪にはアテができます。永い年月が経過してこの木が伐採され、アテのできた年を調べれば、災害があった年が特定できるのです。また、地滑りなどのようにゆっくりとした地表変動の場合、人間には感じ取れない微妙な地形の傾きであっても、樹木は直立を保とうとするのでアテが生じます。一般的に針葉樹の場合、木に力が加わると圧縮される方の材部にアテが生じます。広葉樹の場合はこの逆方向にアテが生じます。このことを上手に利用すれば、アテの起き始めた年とアテの向きを調べることで、いつ頃からどちらの方向に向って地滑りが起きたかということを推定することができるのです。