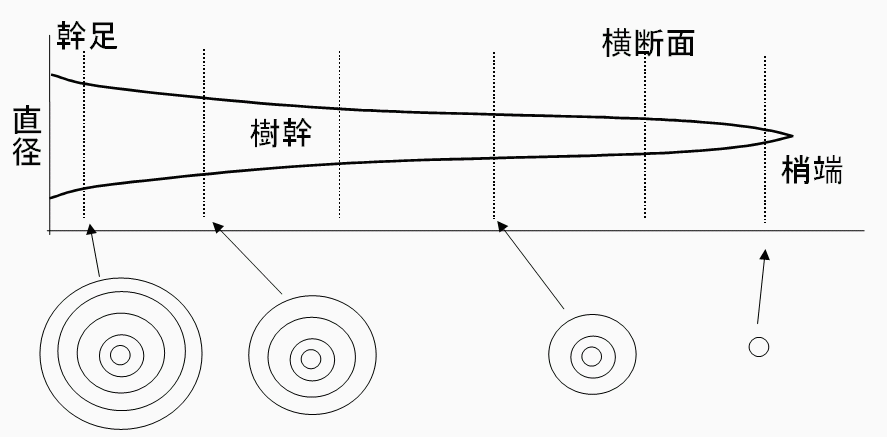
何故樹幹解析をするのか
樹木の幹から木材を採取して利用しようとする際、幹部の体積の把握は重要な課題といえます。また、林業経営者にとって過去の成長経過を知ることは将来の計画を立案する上で極めて重要な課題といえます。樹幹解析はこのような目的を達成するために考えられたもので、精密な樹幹の体積を把握する手法といえます。
樹幹解析は樹木の幹についていくつかの高さから円板を採取してそれぞれの年輪幅を調べることにより、幹の体積や過去の樹高成長経過を精密に調べる方法である。円板を採取する位置は解析の目的応じて様々であり一定ではないが、通常は図に示すように、伐倒した幹の高さ0.2m, 1.2m, 3.2m,・・・, .2m, 10.2mというように2m間隔で幹から円板を採取し、梢端(top end)が3m未満の場合は1m間隔で円板を採取する。
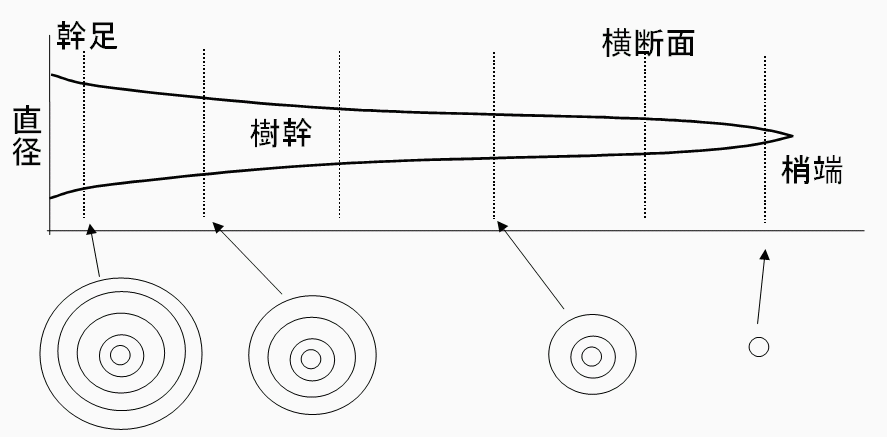
胸高(1.2m)直径を基準として幹の材積を求めるために用いられる我が国では一般的な方法である。幹の根元、幹足(butt end)や梢端部は形の変化が激しいため円板採取間隔が短く設定されている。
高さ0.2mの位置から得られた円板の年輪数に0.2mの樹高に達する年数を加算したものが解析樹木の樹齢となる。各円板については最外周の年輪は伐採年に形成されたものなので、この年輪からさかのぼるように年輪幅を測定すると、年輪が形成された年を特定することが容易となる。測定方向は通常4方向で、5年毎の年輪を計測する場合が多い。この段階で各断面高における肥大成長の経過を読み取ることができる。また、各円板の最も中心よりの年輪は樹木がこの高さまで成長したことを示しているので、中心部の年輪の樹齢から伸長成長が推定できる。さらに、胸高直径と樹高の成長経過から過去の材積成長を推定することができる。
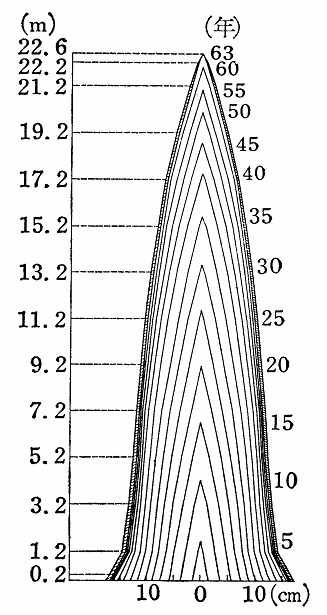
断面毎の年輪幅を読み取ることで
1.過去の樹高が把握できます。
なお、樹高推定の精度は断面の間隔によることになります。
2.幹の過去の材積が把握できます。
樹幹解析をコンピュータ上で行う場合は「SDA」というアプリケーションソフトが利用できます。