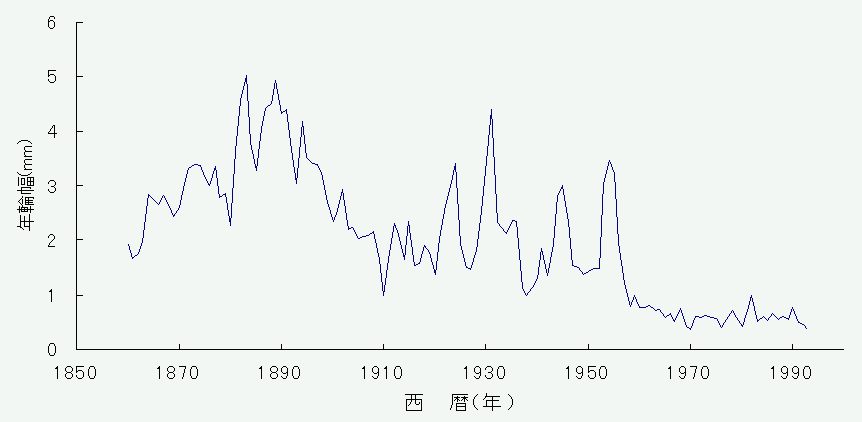
肥大成長の実測値
下図は山形県羽黒山に成育する天然生アカマツの年輪幅の年変動を示している。このアカマツの肥大成長はゴンペルツ曲線に類似しているようにみえるが、近似曲線からの変異はかなり大きいことが予想される。
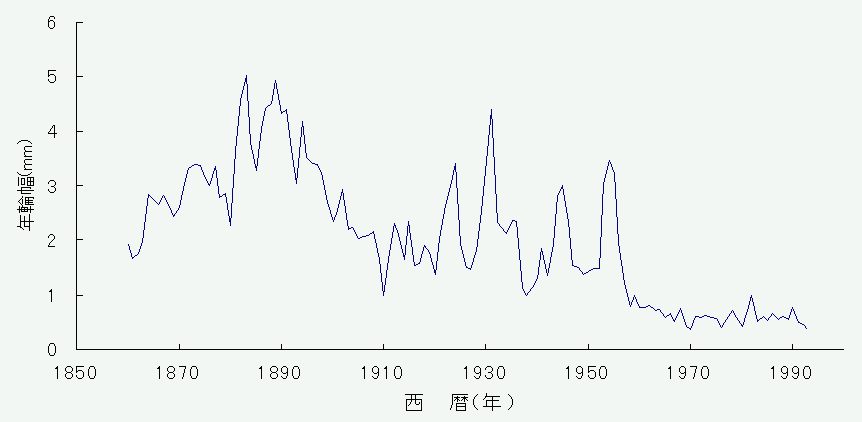
羽黒山アカマツ実測年輪幅
林業では樹種や立地ごとに理論的な成長曲線を予測することで木材収穫に関する経営計画を立案することができる。一方、理論的な成長曲線からの隔たりを調べれば、変動の原因となる要素を抽出することができる。そのひとつ周囲の木々との関わりでありもうひとつは環境の要素である。年輪幅変動にはこのほかにも遺伝的性質などいくつかの要素が含まれていると考えられている。
年輪幅データの標準化
一定の地域内に生育する同一樹種の樹木は気象など環境要素の影響を一様に受けるため、年輪幅の相対的変動は同じように変化する。しかし、年輪幅の変動には成長の特性、周囲の樹木との競争の影響、環境の影響など様々な情報が混在して取り込まれているため、環境要素だけを取り出すためには個々の樹木の成長特性や周囲の樹木との競争の影響を取り除く必要がある。年輪幅の変動に含まれる情報の中で成長の特性については、理論成長曲線、スプライン曲線や移動平均などの傾向曲線で近似できる。各年の年輪幅はこれらの傾向曲線を中心として上下に変動している。当該年の年輪幅を傾向曲線上の当該年の数値で除すと変動量だけを取り出すことができる。この作業を標準化という。
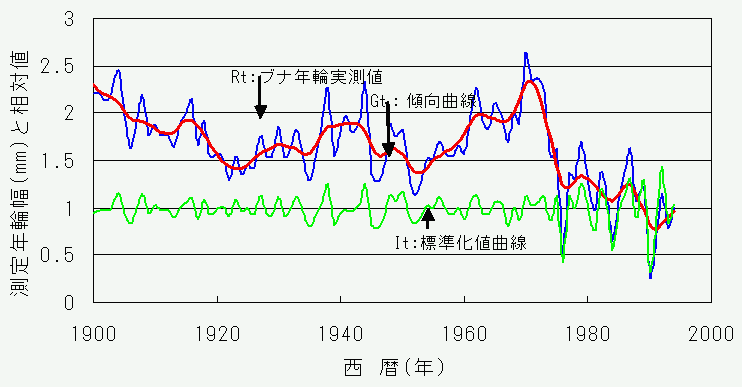
スプラインによる傾向曲線と標準化年輪幅曲線
標準年輪曲線
ここで得られた標準化年輪幅データには周囲の樹木との競争の影響と環境の影響が含まれており、成長の特性が取り除かれている。周囲の樹木との競争の影響については、複数の樹木から得られた標準化年輪幅のデータを平均することで取り除くことができる。このようにして得られた年輪幅の時系列データを標準年輪曲線(index tree ring width)という。ただし、複数の樹木の標準化年輪幅データを平均する場合、それぞれの樹木の標準化年輪幅がお互いに同調して変動していることが条件となる。標準年輪曲線を作成する際の世界的な標準は一地域内に生育する同一樹種樹木10本以上につき、100年以上の年輪を1本につき2〜4方向計測し、これらのデータを基に作成することとされており、成長傾向を代表する曲線としてはスプライン曲線を使用する場合が多い。
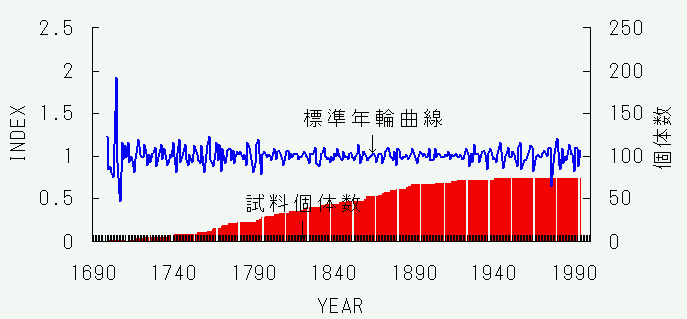
北日本全域におけるブナの標準年輪曲線
クロスデーティング
我が国では局所気候の変化が激しいため標準年輪曲線の作成には懐疑的な見解がこれまで主流であったが、木曽のヒノキや北海道のアカエゾマツなどでは90%以上の樹木で年輪幅の変動が同調していることが示されるようになり、徐々に標準年輪曲線の作成が進められるようになっている。この標準年輪曲線と生育年代が不詳な樹木の標準化年輪幅のデータを一年づつずらしながら相関係数を計算していくと、あるところで相関値が突出して高い年が出現する。この位置が年代不詳の樹木の生育年代と推定できる。この手法をクロスデーティング(crossdating)という。この手法を応用して木材の年代鑑定が行えることから、考古学へも応用されている。また、古代建築や埋もれ木などの年輪幅情報を積算することで、標準年輪曲線の過去への延長も可能である。この標準年輪曲線には環境の影響が最も強く関与していると考えられることから、過去の気候状況の復元などにも応用されている。このような学問分野を年輪気候学(Dendroclimatology)という。
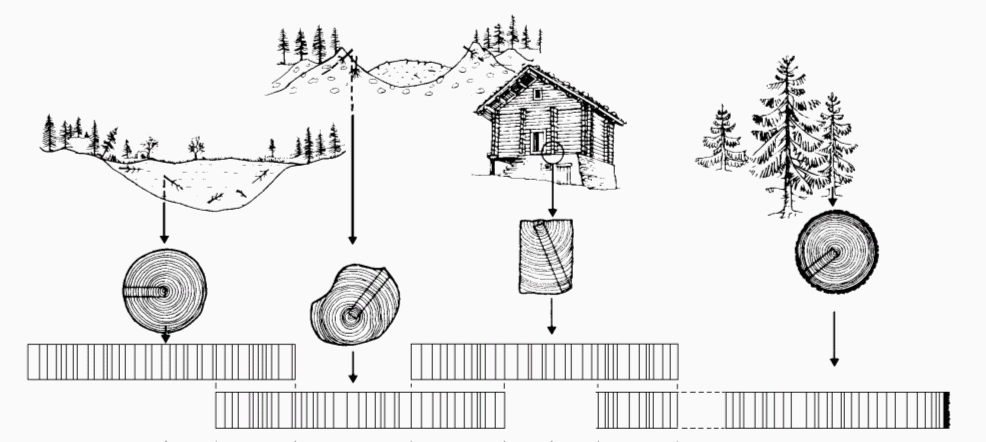
クロスデーティングの考え方
注:注:Schweingruber, F. H. (1988) Tree Ringsをもとにして作成した。